友よ、
友よ、
クリスマスは、あまりに遠い
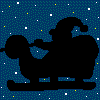 書斎の整理をしているとき、懐かしい手紙が出てきた。数年前、
書斎の整理をしているとき、懐かしい手紙が出てきた。数年前、
年の瀬も近い頃、古くからの友人からもらった手紙だ。村上春樹
の「中国行きのスロウ・ボート」のパロディだ。
受け取ったばかりのときは、思わず吹き出した記憶があるが、
今あらためて読み返してみると、なかなか味がある。カレーは一
日寝かしたほうが上手い、とコマーシャルで流れていたが、手紙
も5、6年寝かしたほうが、おいしく感じられるのかも知れない。
あの頃、恋人たちがロマンチックに盛り上がるクリスマスは、
僕たちにはたしかに縁遠いものだった。

「いいね、君の肩にかかっているんだよ。最近の情けない男に気
合を入れてやってほしいんだよ。ほんでもってついでに、近頃の
生意気な女どもにだな、こうストレートにガツーンと言ってやっ
てほしいんだ」
そう言うと編集長は、わけもなく腕をブンブンと振り回す。
この人は昔から、興奮すると足を大きく一歩前に突きだし腰を屈
め、腕を振り回す癖がある。
「やだよ、この人は。そんなこと言ったって、つい最近までは僕
らだって情けない男の代名詞だったじゃないですか。まぁ、今が
違うってわけでもないけれど・・・」
なんてことを、口に出してはいけない。締切まじかの週末の編
集室には、全スタッフが詰めかけ、緊張感がみなぎっている。秒
読みとなった入稿をひかえ、みな必死の形相で机に向かっている。
たとえその手元が、実際には帰り支度にいそしんでいたとしても、
そんなことは関係ない。僕らにも面子というものがある。
ここは気難しげに口をへの字に結び、腕を組み、二十五秒数えて
から、おもむろに口を開く。
「そうなんですよね。最近の若者の群衆心理をフロイト的に分析し
ますと・・・」
自分でも何を言っているのかよくわからないのだが、編集長は
「そう、そう」と、大きくうなずいてくれる。僕はますます調子に
のって、ユングまで持ち出す。
と、そのとき、ミニラ(ゴジラの息子)が吐き出したような白い
だ円が、僕の鼻先をかすめて漂ってきた。だ円の先をたどると、恋
多き女のエミリーが足を組み、タバコを吸っている。煙をそっと口
から吐くと、次の瞬間、エミリーはニヒルな笑みを向けてきた。
この女できる、ただ者ではないなーー、すべてを見透かされてい
る気がして、僕は思わず視線を外らした。

クリスマスの彩りに町が染まる頃、僕らはよく歌っていた。
「シングルベッド、シングルベッド、来年もシングルベッド」
男ばかりが集まって歌ったこの曲は、街頭の手相見よりはるかに
正確に、僕らの明くる年を予言していた。
もっと長いサイクルでも、それほど事態は変わらなかった。
御柱がやってくると、僕らはよく深夜に柱の近くに集まった。闇の
中、月明りに浮かぶ御柱にまたがっては、
「いやぁ、今度の御柱のときには、もうみんな結婚してるんだろう
ね。子供といっしょに曳いてたりしてね、ハハハ・・・」
などと、互いに言い合っていた。
そのくせ七年がたち、また御柱がやってくると、結局は同じこと
を口にして笑っている。
「あれ、このセリフ、前も言ったような気がするなぁ、ハハハ・・・」
白々とした夜が明けてゆくのを、僕らは心持ち楽しみながら過ご
した。そんな御柱が、何回か繰り返された。
断っておくが、僕らがまったくもてなかったわけではない。
ーーと思う。
もてた事実がないだけのことだ。まぁその辺は、見解の相違ってや
つだ。
自分で言うのもなんなんだけど、僕らに付けられる形容詞で、も
っとも多かったのが「いい人」だった。好きになった人ごとに、
「あなたはいい人」なんて言われるものだから、つい浮かれて、こ
れにはきっと素晴らしい意味があるに違いないと思い、国語辞書で
引いたことがある。
「いい人」とは、「善良な人。ときにお人好し」と説明されている。
それ以上のニュアンスは、辞書をどうひっくり返しても出てはこな
い。要するに、お人好しと誉めらているにすぎないことがわかり、
僕はあらためてショックを受けた。
ついでにある女性雑誌をめくっていたとき、「『いい人』とは、
友達以上の関係になれない人を指して使用される。つまり恋愛の対
象としては絶対に見ることのできない人のことである」という文を
見つけ、色めき立った。
そうだったのか、僕の今まで抱いていた疑問は一気に吹っ飛んだ。
誉められるほどに好感をもたれていたにもかかわらず、あの手この
手を尽くしてもどうしても恋人までに発展しなかったのは、そうい
う理由があったのか。それは、涙が出るほどにうれしい発見だった。
それ以後、仲間うちの誰かが「俺、彼女に『あなたは本当にいい
人』って告白されちゃったんだ。今度は上手くいきそうだ。ヘヘヘ・・・」
なんてのたまっているのを聞くと、つい講釈を垂れる癖がついてし
まった。
聞いた本人の顔から血の気が引くのはよくわかる。だがそれ以上
に、今まではやし立てていた仲間たちが「それ本当のことなのか」
とあわてふためく姿を見ると、彼らも「いい人」と言われて浮かれ
ていた口に違いないと、納得せざるを得ない。
先ほどまでの騒々しさが消え、店内は静まり返る。僕らがたまり
場にしていた小さなライブハウスは、夜も十一時をすぎると、客足
がばったり途絶える。男ばかりが黙り込んだまま、それぞれ物思い
にふけり、グラスを空けている姿は、それなりにさまになる。ただ
ひとつだけ難を言えば、グラスの中身が、ただの水だったことだろ
うか。連日集まる「いい人」たちの共通項は、金がないことだった。
「クリスマス・パーティーをやろう。」
誰かが不意に口に出した。
「クリスマスの夜にロマンチックなコンサートを開けば、きっと若
い女性だけのグループが来てくれるさ。そうすれば、今年のクリス
マスは賑やかになるぞ」
仲間の瞳があやしく輝きだした。やろう、やろう、クリスマスの
夜にパーティーを開こう、全員一致で話は軌道にのった。
コンサートと言っても、ロックとは無縁だ。狭いライブハウスは
アコースティック専門だった。古いストーブの上に作られた空間が、
僕らのステージだ。過ぎ去った日のフォークソングや、私小説その
ままのオリジナルソングが、西部劇を思わせるそのライブハウスに、
よく似合っていた。
ときたま店に女の子だけのグループが入ってくると、僕らは先を
争ってクリスマスの夜の素敵な企画について紹介し、ぜひ遊びにき
てくれるように頼んだ。感触はおおむね良好だった。この分だと、
席が足りなくなるかもしれないと、僕らはほくそ笑んだ。
クリスマスに向け、僕らの胸はときめく。聖なる夜を境に、きっ
となにかが変わるに違いないという確信が、僕らにはあった。だか
ら飾り付けも前日から入念にした。クリスマスソングもきちんと覚
えた。ヤマザキのケーキとチキンもそろえた。
そして当日、おあつらえ向きに粉雪が舞い出した。雰囲気は最高
潮に達している。僕らはワクワクしながら、扉を見つめる。
一人二人と客は入ってくる。いつもの常連さんだ。三人四人五人
と客は入ってくる。このビルのオーナーとその友人たちだ。六人目
も七人目も、やっぱりたまに見かける男の客だ。
テーブルは徐々に埋まっていく。なのに、なのに、肝心の女性客
の姿がちっとも見えない。仲間の顔に次第に焦りが浮かんでくる。
そのとき誰かが叫んだ。「来た。来たぞ。ついに来たんだ」扉に
全員の視線が釘付けになる。以前に声をかけた女性が、はにかむよ
うな笑みを浮かべて立っているではないか。僕らは狂喜乱舞した。
クリスマスの夜に初めて見る女性である。
だがその三秒後、みな一様にあんぐりと開いた口が塞がらない状
況を迎えることとなった。あとから男がついて入って来たのである。
なんのことはない。カップルで来たのだ。全員の笑みが一瞬こわば
る。
結局のところその夜、女性だけのグループは、一組も現れなかっ
た。女性というやつはクリスマスの聖なる夜に、同性だけで外に飲
みに行く習性はないらしい。だが男は違う。男は聖夜に群れ集うの
である。現に店内はむさぐるしい男どもで埋められている。僕らは
気落ちした素振りを悟られないように、努めて明るく振舞った。
それでも酔っ払いの男ばかりが集まり、さだまさしの「防人の歌」
なんてリクエストされた日にゃ、いやが応でも気分は盛り下がる。
何が悲しゅうてこんなロマンチックな夜に、行き場のない男どもの
ためにこんな泣ける歌を唄わなけりゃいけないのか、つくづく情け
なくなってくる。
結局はなにも変わらなかった。その年のクリスマスは、男ばかり
が集い、歌い、そして過ぎて行った。
「やっぱ今年はさ、ケーキが小さすぎたんだよ。来年はさ、チョコ
レートの家がのっかってる大きなケーキにしようよ。ハハハ・・・」
誰かがそう言うと、そうだ、そうだ、来年こそはヤングレディに
囲まれたクリスマスにしよう、と僕らは祝杯を上げた。グラスには、
同情したマスターの恵んでくれた期限切れの牛乳が、満たされてい
た。
だが次の年も、その次の年も、事態は大して変わらなかった。問
題はケーキではなかったようだ。どんな企画をたてようと、聖夜に
集まってくるのは、やはり男ばかりだった。
客の途絶えた深夜、僕らは言葉少なに降り積る雪を見ていた。時
折通り過ぎるアベックの笑い合う声が、店内にまで響いた。
やがて僕らは眠りについた。酒を飲んで酔っ払ったやつも、一滴
も飲んでないのにただ眠くなったやつも、いつのまにか机に突っ伏
したまま寝息をたてはじめている。その不器用な男たちの背中から
は、そこはかとない哀愁が立ち上っていた。ーーと思う。
遠ざかる意識の中、マスターがひとり煙草をくゆらせながらつぶ
やいた。
「もう今年も終りか」
クリスマスの夜、時計の針が十二時を回る頃、部屋の窓をそっと
開けてみてほしい。聖夜のしじまに流れる孤独な者たちの悲しみを、
ほんのすこしだけでも感じることができるかも知れない。それは、
星々の悲しみには及ばないだろうけれど・・・。
今年、聖夜を恋人とともに過ごせる人も、そうでなかった人も、
来年があなたにとっていい年でありますように、乾杯。
そして、メリークリスマス・・・。
(ドン・ヤマモト)
上テキストは、「月刊LIVE STATION」12月号に掲載されたものです。
 クリスマスについて知りたい方は、このドアをノックしてください。
クリスマスについて知りたい方は、このドアをノックしてください。
南信州ペン倶楽部のホームページにもどる
 DON-SPS のホームページへもどる
DON-SPS のホームページへもどる
書斎の整理をしているとき、懐かしい手紙が出てきた。数年前、